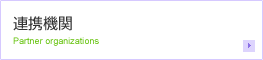記事詳細
2024年10月09日
【プレスリリース】本田諒准教授らの研究グループがALS、アルツハイマー病の早期診断に向けた新たな技術を開発しました
本研究科の本田諒准教授、大学院医学系研究科の下畑享良教授、岐阜薬科大学の位田雅俊教授らのグループは、神経変性疾患の発症に関わるTDP-431) およびアミロイドβ2) 凝集体の超高感度検出技術を開発しました。この技術は、新たに発見された「Brij-583)」という特異な性質をもつ界面活性剤を使用することによって、従来のシード増幅アッセイ法(SAA法4))の検出感度を飛躍的に向上させたものです。この技術により、最小5フェムトグラムという超微量の凝集体の検出が実現し、実際の患者の脳組織に蓄積した病的凝集体を検出することも可能となりました。本技術は、将来的にはALSなどの神経変性疾患の早期診断や早期治療介入に貢献することが期待されます。
本成果は、日本時間2024年10月8日にTranslational Neurodegeneration誌のオンライン版で発表されました。
[用語解説]
1) TDP-43: 筋萎縮性側索硬化症、前頭側頭型認知症などに関連する異常なタンパク質の一種。
2) アミロイドβ: アルツハイマー病などに関連する異常なタンパク質の一種。
3) Brij-58: 界面活性剤の一種で、本研究でSAA法の検出感度を飛躍的に向上することが明ら
かになった。
4) SAA法:シード増幅アッセイ法、もしくはSeed Amplification Assay法。病的なタンパク
質凝集体を試験管内で増幅することで、超高感度検出を可能とする技術である。
プリオン病、パーキンソン病の早期診断法への応用研究が進んでいるが、TDP-43
やアミロイドβ凝集体の検出は困難であった。
ALS、アルツハイマー病の早期診断に向けた新たな技術開発 ~病因タンパク質TDP-43、アミロイドβを超高感度で検出可能に~
詳細な内容は岐阜大学のHPからご覧いただけます。